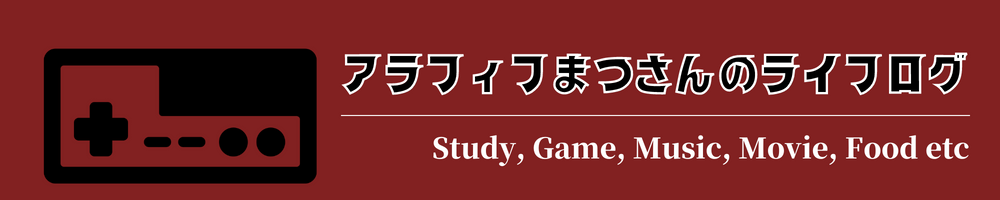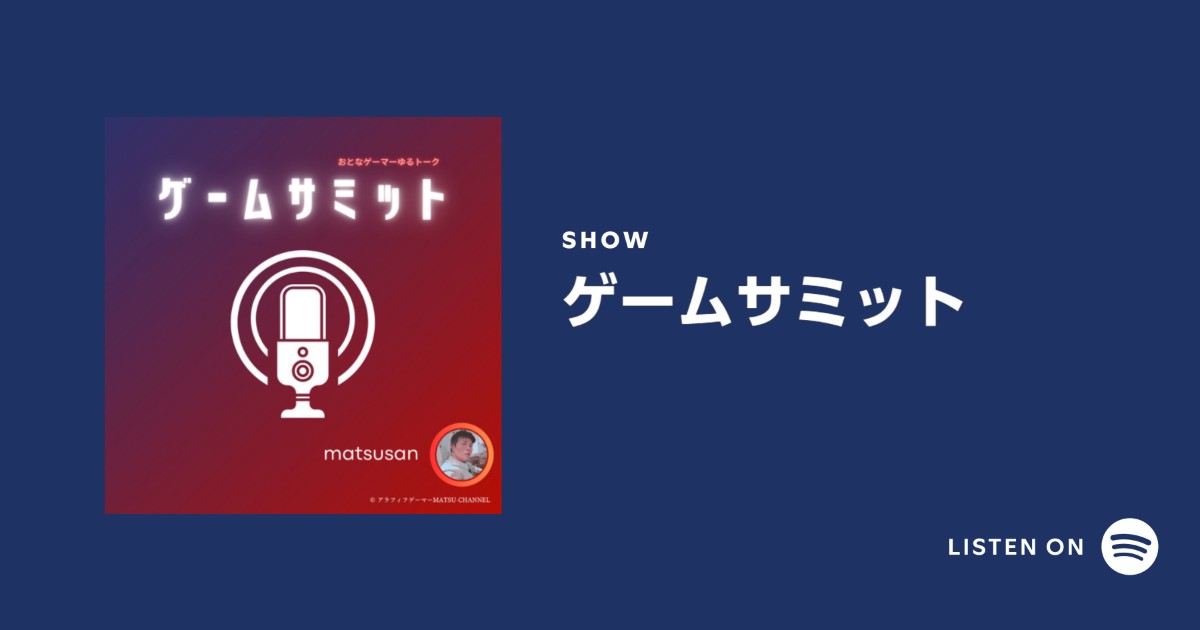ポッドキャスト概要:モンスターハンター体験とゲーム難易度の考察
導入
本エピソードは、ナビゲーターのまつさんが、最近のゲームプレイ体験、特に『モンスターハンター』シリーズへの再熱について語り始めます。まつさんは、以前は別のゲーム(Expedition 33)に集中していたため『モンスターハンター』から離れていましたが、6月末のタイトルアップデートを機に再開し、8月と9月はほぼ毎日配信で『モンスターハンターワイルス』をプレイしていたとのことです。
第1部:ナビゲーターの『モンスターハンター』体験(8月・9月)
アップデートと季節イベント
6月末には、過去シリーズに登場したラギアクルスとセルレギオスという2体のモンスターが追加されました。その後、季節イベントとして、既存のモンスターであるウズツナの特殊個体、歴戦王ウズトゥナのチャレンジクエストが実装されました。
- ウズトゥナは元々ゲーム発売当初から実装されていた「緋の森」エリアの頂点モンスターですが、報酬的な魅力が薄く、まつさんはあまり足を踏み入れていませんでした。
- 久々に挑戦したこのチャレンジクエストが予想外に楽しく、タイムアタック形式でSランク(12分以内)を目指し、最終的には狩猟笛という武器を使い、目標の10分以内を達成して堪能しました。
エンドコンテンツ「光るお守り」の沼
8月13日には、秋に予定されていたエンドコンテンツである光るお守りが実装されました。
- お守りの仕様: 『モンスターハンター』には、会心率や攻撃力の向上、切れ味の持続など様々な「スキル」がありますが、お守りにはこれらのスキルがランダムに組み合わされて配置されています。鑑定後にお守りを装備することで、スキルが追加されます。
- このシステムは「沼の仕様」と表現されており、スキル内容自体は控えめ(渋め)であるものの、ランダム要素と「コンマ何パーセントでも火力を上げたい」というプレイヤーの強い欲求により、熱中してしまう要素となっています。
- 過去作(『モンスターハンターワールド:アイスボーン』)のミラボレアス素材で作れたような破格の装備に比べると、インフレを抑え気味な性能である点が特徴です。
お守り掘りのクエスト周回
お盆以降は、光るお守り堀と、クエストランクが一段階上がった6月追加モンスターのクエストを周回しました。
- お守りはクエスト終了時に即座に鑑定される仕様です。
- モンスターによってお守りの出現枠数に差があり、最大10個出るモンスターと最大5個しか出ないモンスターがいます。6月に追加されたラギアクルスとセルレギオスは10枠モンスターだったため、これら2体をひたすら狩猟しました。
- 特にラギアクルスは、当初は立ち回りが難しかったものの、プレイするうちに面白さを見出し、体力が一定以下で挟まれる水中戦の要素も駆使しながら、最高ランクのクエストで6分台のタイムを出すことに成功しました。
FFXIVコラボモンスター討伐
9月29日には、国内トップMMOゲーム『ファイナルファンタジー14』とのコラボモンスター、オメガプラテネスが実装され、まつさんはサポートハンター(NPC)と共にソロで初見クリアを果たしました。
- このモンスターは「高難易度クエスト」と言われており、前々作のコラボモンスター「ベヒーモス」と比較して、個人的にはやりやすいと感じたそうです。
- 同日には、高難度の零式オメガプラテネスも実装され、まつさんは初日に挑戦。一度は失敗したものの、翌9月30日にサポートハンターと共に見事討伐に成功(制限時間35分に対し、34分30秒でギリギリ討伐)。その後、配信でフレンドやリスナーとも成功を収め、非常に楽しんだとのことです。
第2部:ゲームにおける難易度:Easyモードの考察
ここから、本エピソードのメインテーマである「ゲームにおける難易度、Easyモードはありかなしか」という議論に移ります。
Easyモードのメリット
Easyモードの最大の利点は、誰でも安心して遊べる点です。
- ストーリー体験の保証: ゲームが得意でなくても、最後までストーリーを体験できます(「ストーリーモード」として採用される場合もあります)。
- 敷居の低さ: 時間がない人や忙しい人でも短時間で遊ぶことができ、多くの人にとってありがたい存在となっています。
まつさんがEasyモードを選ぶ場面
まつさん自身もEasyモードを選ぶ場面があるとしています。
- 効率重視の周回: PlayStationのトロフィーやXboxの実績などの「やり込み要素」をコンプリートするために周回が必要な際。既にノーマルモードでクリアしており、効率を重視する場合はEasyモードを選択します。
- 苦手要素の回避: アドベンチャーゲームにシミュレーション要素が組み込まれているゲーム(例:アトラスの『十三機兵防衛圏』など)。まつさんがシミュレーション系を苦手としているため、その部分をプレイする際にEasyモードを使用することがあります。
Easyモードのデメリットと失われる体験
Easyモードを選択することで、開発者が意図した攻略体験やゲーム本来の面白さが失われてしまう可能性があるという点がデメリットとして挙げられます。
- 開発意図のスキップ: 特殊なシステムを理解し、活用することで面白さが見えてくる構造のゲームであっても、Easyモードではシステムを理解せずに「ゴリ押し」で進めてしまう可能性があります。その結果、革新的なシステムや本来の面白さを知ることなく終わってしまうかもしれません。
- 達成感の減退: ゲームをクリアした際の達成感や、困難を乗り越えた手応えが弱まってしまうという点もデメリットです。
難易度論:フェアな難しさと理不尽さの違い
ゲームの難易度設定において重要なのは、「難しい」ことと「理不尽」なことの違いです。
- フェアな難しさ(アリな難易度):
- フロム・ソフトウェアの『ダークソウル』や『SEKIRO』などの高難易度ゲームは、フェアな難しさとして評価されています。
- 『ダークソウル』では装備やレベル上げ、『SEKIRO』では弾きや体幹崩しといったシステムを理解し活用することで、クリアできるように設計されています。この「フェアさ」こそが、ゲームに挑戦する楽しさにつながっているとまつさんは考えています。
- 特に『ソウル』シリーズは、初心者でも達成感を得られ、上級者はレベル1クリアやタイムアタックなど様々な楽しみ方ができるため、支持されています。
- 理不尽な難しさ(ナシな難易度):
- これはプレイヤーにとって「ただのストレス」であり、リプレイ性にも繋がりません。
- 例として、説明不足のまま強敵が出現する、解法が全く分からない、運に左右されすぎる、などが挙げられます。
- まつさんが特に嫌うのは、プレイヤーのキーログを見て超反応で行動を潰してくるゲームです。これはフェアではないと判断しています。
- フェアなゲームの例: 『バットマン』、『スパイダーマン』、『ベヨネッタ』。
- アンフェアなゲームの例: 『龍が如く』シリーズのアクション部分は、超反応でキー入力を見ていると感じられ、まつさんは楽しさを見出せないと述べています。
まつさんは、オンライン要素やリプレイ性を求めるゲームは、フェアであることが前提であるべきだと結論付けています。
第3部:まつさんの結論とEasyモードの理想像
Easyモードは「全然アリ」
まつさんの結論としては、Easyモードは全然アリです。
- 難しくて面白いゲームが最後までプレイできないのはもったいないため、難易度を下げてでもストーリーやアクションを楽しんでほしいという考えです。
理想的な難易度設定
ただし、開発者に向けては、プレイヤーがシステムの大部分を使わなくても進めてしまうような設計ではなく、あくまでフェアな範囲で難易度を下げることが理想であると提言しています。せっかく実装した革新的なシステムが使われないのでは意味がないため、うまくプレイに反映できる難易度設定を求めています。
『ベヨネッタ』のEasyモードを例に
例として『ベヨネッタ』のEasyモードが挙げられています。
- 『ベヨネッタ』のEasyモードでは、コンボアクションがオートで出る(ボタン連打で自動回避やコンボ接続)仕様になっています。
- まつさんは、これは「やりすぎ」ではないか、本当に面白さに繋がっているのか疑問に感じると述べています。
- 『ベヨネッタ』のアクションの面白さは、プレイヤー自身が意識して技を組み立てたり、「ダッジオフセット」などのテクニックを使ってコンボを途切れさせないようにすることにあります。オートコンボはその体験を損なってしまうため、Easyモードをクリアした後でもノーマルモードに挑戦してほしいという意見です。
まつさんは、プレイヤーの目的に合わせて柔軟に楽しめるようにするEasyモードの存在こそが、ゲームの奥深さを示しているのではないかと締めくくっています。